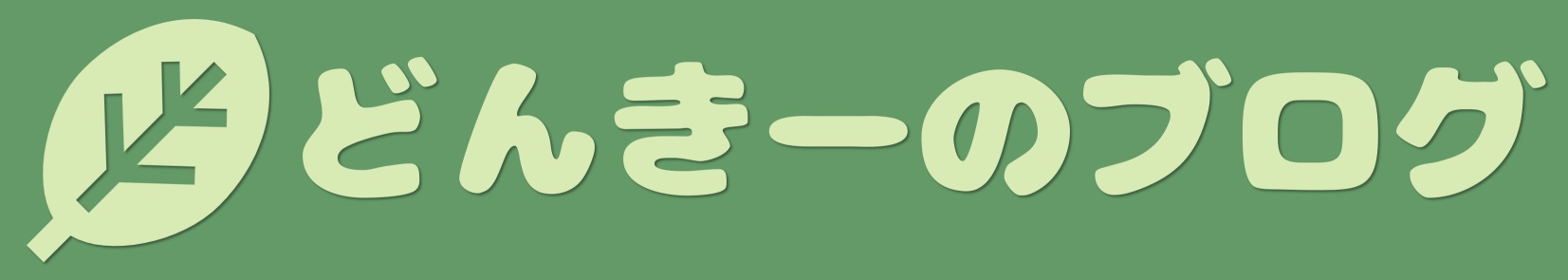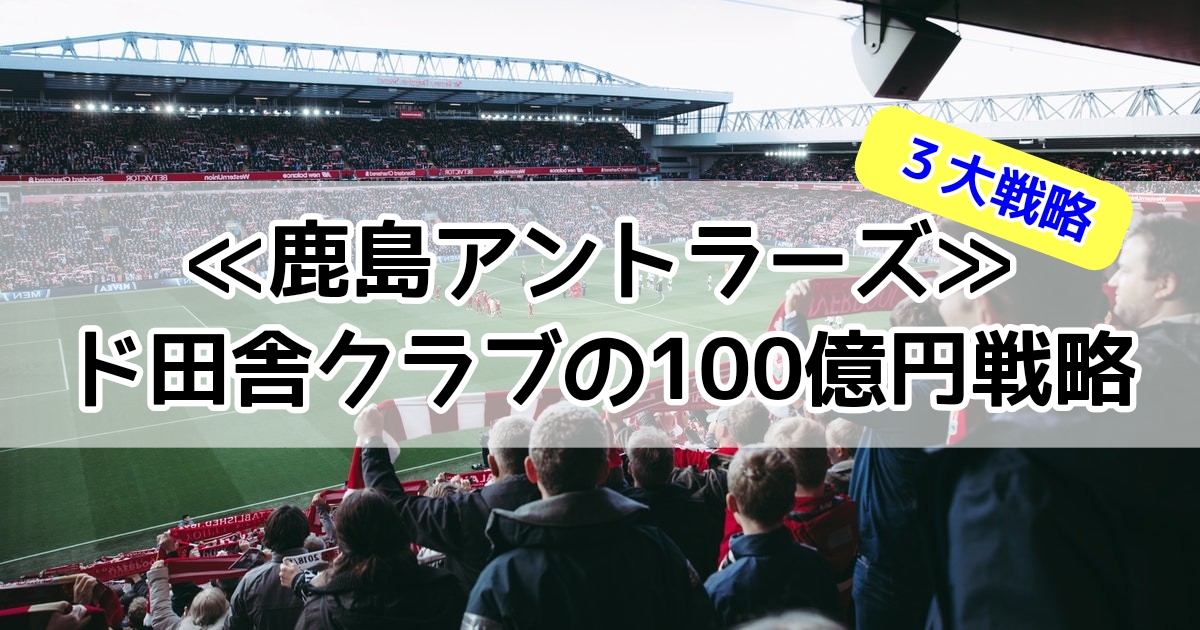今回は、Jリーグの鹿島アントラーズの戦略についてご紹介します。
クラブ経営のビジネス環境としては、決して恵まれた環境ではないにもかかわらず、Jリーグ発足から継続してJ1リーグで戦うことができているのはなぜなのか。Jリーグ加盟のバックグラウンドから最新の経営戦略まで、ご紹介します。
- 鹿島アントラーズの成り立ちとジーコ
- 鹿島アントラーズのビジネス環境
- ド田舎クラブの最新テクノロジー戦略
鹿島アントラーズというクラブ・会社

鹿島アントラーズの成り立ちと実績についてです。鹿島アントラーズを語るうえで欠かせないジーコが植え付けたプロ意識や、商圏や売り上げなどのビジネス視点で見た鹿島アントラーズを取り巻く環境について紹介します。
成り立ちと実績
- Jリーグ発足前、鹿島アントラーズの前身である住友金属工業蹴球部は日本サッカーリーグで2部所属
- 住友金属だけでなく、鹿島町(現鹿嶋市)長と一丸となってJリーグへの参加を表明
- 設立準備メンバーである川渕三郎氏が、住友金属のJリーグ加盟を諦めさせるため、屋根付きスタジアム建設を条件としたところ、茨城県が建設を決定。逆転でのJリーグ加盟が認められた
鹿島アントラーズのJリーグ加盟について、川渕さん自身も印象的な出来事としてインタビューで語っています。
とにかく住金が加入できる確率は限りなくゼロに近く、99.9999%ダメだったと思いますね(笑)。それはそうでしょう。他チームに比べてホームタウンとなる地域の人口が少なく、しかも弱いし、スタープレーヤーもいない、競技場もないと、いいところなしだったんですからね。
鹿島アントラーズ-鹿島アントラーズ誕生物語 >> DRAMA Vol.14 0.0001%の可能性
それで「日本で初めての屋根付きの専用競技場でもできれば、話は別ですがね」と冗談のつもりで言ったら、茨城県へ働きかけはじめたんです。私は困ったなと思い、「競技場ができても、観客が少なくてガラガラでは話になりませんよ」と言ったら、今度は近隣の町村長や各団体のハンコを押した書類の山を見せられました(笑)。県や町、地元企業の協力をとりつけたというわけです。
ジーコのプロ意識
- 住友金属工業蹴球団は日本リーグ1部と2部をいったりきたり
- 1991年にジーコが加入し、アマチュア集団であった選手らプロ意識を根付かせていった
- プレー面だけでなく、ファンへの接し方や道具を大切にする姿勢などの精神面でもプロ意識を植え付けていった
- フロントやクラブスタッフに対しても、プロ意識を求めており、クラブハウスや用具係の充実など、選手がサッカーに集中できる環境を作り上げることを常々言い続けていた
ジーコはプロ意識を根付かせるべく、選手はもちろんスタッフに対しても様々な言葉を掛けています。「ゴールにパスしろ」、「練習の後で疲れているのはよくわかる。でも、雨などで身体が冷える恐れがない限り、20分程度でいいので必ずファンと接するように。俺たちがサッカーで食べて生活していけるのはファンのおかげだからだ」など。
他にもジーコはあらゆる名言を残しており、こちらでまとめてご紹介しています。
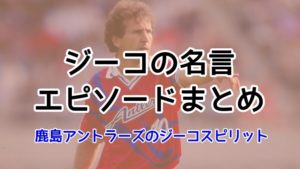
日本での鹿島アントラーズ
鹿島アントラーズというサッカークラブの商圏や観客の特性、売上について。
商圏
- ホームタウン鹿嶋市の人口は6万7千人
- 一般的にクラブ経営に最低限必要とされている半径30km人口は100万人と言われている
- それに対し、鹿島アントラーズは沿岸部にあることもあり78万人
- 他のクラブは、FC東京は2300万人、浦和レッズは1800万人であり、大きな差がある
首都圏のクラブに比べれば商圏としてはだいぶハンデを抱えていることが分かります。
観客
- スタジアム収容人数4万人に対し、平均2万人の観客数
- 観客数の地域別構成比は、30km圏内25%、東京など首都圏からは50%
- 観客の女性比率はリーグトップ
都心から距離があり、試合がある日にはアクセスに2,3時間かかることもあります。
売上
- J1売上平均30億円弱に対し、鹿島は70億円
- 世界標準は100億円であり、鹿島をこれを目標にしている
2018年度は、過去最高の73億円の営業収入と決算発表がありました。2016年、2018年にはクラブワールドカップでレアルマドリードと対戦し、レアルマドリードを間近に見ながらクラブ運営についてもヒントを得ることができたようです。
- 一般的にはスタッフ数=選手数
- 鹿島アントラーズのメディカルスタッフは3人。それに対し、レアルは9人
- 鹿島アントラーズのドクターは1人に対し、レアル3人
- レアルマドリードの売上高は870億円
鹿島アントラーズの戦略
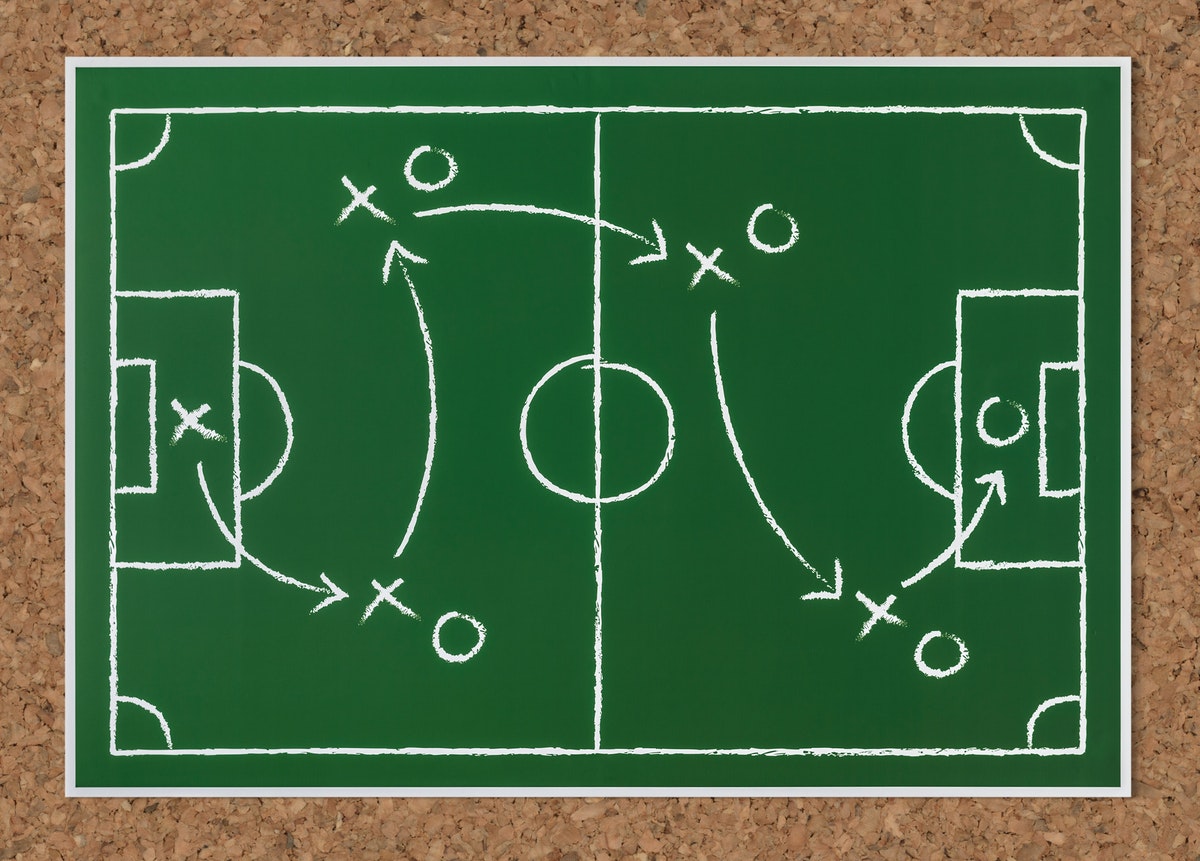
直近のクラブ幹部へのインタビューにおいて、鹿島アントラーズのこれからの経営戦略について語られています。
スタジアム規模を4万人から2万5千人へ
- ホームスタジアムのカシマスタジアムでは、ワールドカップの試合の催行経験もあり、東京オリンピックの会場にも選ばれている
- 日本では、スタジアム事業は公共性が求められ、思うような経営がしづらい現状がある
- 鹿島アントラーズは、人口7000万人社会を見据えてスタジアム規模を2万5千人程度までに減少させることを考えている
- カシマスタジアムでの観客の50%を占めるのは東京からのサポーターであり、比較的裕福な層が多いというデータがある
- 利益を上げるために、VIP戦略の拡充を図っており、2018年は東京からヘリコプターでスタジアムまで移動する観戦プランのトライアルを実行した
- ヨーロッパのクラブ経営の2:8理論を参考にした戦略を考えている(2割の経営者などエグゼクティブ層の入場料収入が、全体の8割を占める)
ド田舎スポーツクラブのデジタルマーケティング
- 地方経営者は、デジタルはとにかく費用対効果が高い魔法のハコと思い込んでおり、分かっているようで分かっていない
- 鹿島アントラーズはスタジアムwifiなどデジタルを活用した取り組みを地道に進めてきており、実績を出し続けることで成長させていった
- 試合会場でのスポンサー地元企業の宣伝に、紙チラシでなく電子クーポンを提案・実行し、地元スポンサーもデータが取れるようになるなど、デジタル化の取り組みではwin-winの関係性を築いてきた
10年後を見据えたクラブ経営
- 高額なスター選手を獲得する戦略でなく、スタッフへの投資を重視している
- スタッフには「10年後どうなるか?」と言葉をかけて、人材育成を行っている
- 事業縮小しながら、選択と集中で利益率を上げていく戦略を検討
- サッカー観戦に温泉をセットにした観戦プランなど、観光業にも取り組んでいる
おわりに
本業の選手育成についても変化が求められています。鹿島アントラーズでは、有望な高卒新人を獲得してじっくり育てるイメージが強いですが、若い選手が早くから海外へ移籍するようになりました。そのため、戦術に合った即戦力を他のクラブから獲得しフィットさせていくことも多くなってきているようです。
J1リーグの試合はもちろん、クラブ運営の面でもユニークな取り組みをしているクラブが多いので今後に注目ですね。